「アイボが来た!」
コロナで変わった病院…11歳の入院生活
2020年8月1日(土) 西日本新聞
福岡県粕屋町の粕屋中央小6年生、清武琳さん(11)は脊柱側そく彎わん症の手術のため、半年に1回、福岡市立こども病院(同市東区)に入院しています。
こども病院には、他の病気にかかりやすい小さな子どもも多く入院しています。
そのため、新型コロナウイルス感染症の対策はとても厳しく行っています。
6月末に10日間入院した清武さんが、対策によって半年前とはずいぶんと変わった病院の様子をリポートしてくれました。
清武さんは、西日本新聞の子ども向け紙面「もの知りこどもタイムズ」に記事を書くこども記者をしていました。
入院中は犬型ロボット「aibo(アイボ)」が病室にやってくるビッグニュースもありました。
手術の2日後、清武特派員の病室に遊びに来たアイボ。丸い目は笑ったり、おこったり表情ゆたかに変化します
★ドキドキのPCR検査
ぼくは脊柱側そく湾わん症の手術のため、半年に1回、福岡市立こども病院に入院しています。
今回は6月末から10日間でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、院内ではいろいろなことが半年前とは変わっていました。
まず、病院の入り口に看護師さんが立ち、入ってくる人全員の体調などを問診でチェックしていました。
カメラで検温され、大きなモニター画面の前に自分の姿と体温が表示されました。
入院する日は最初にPCR検査を受けました。
このときは普段、放射線科の待合室になっているところが、PCR検査専用の部屋になっていました。
看護師さんがガウン、マスク、フェイスシールド、手袋などを着けて検査します。
唾液から検査だったので、そんなに苦痛はありませんでした。
夕方に結果が出るまでドキドキしましたが、陰性と聞いて安心しました。
★読み聞かせ、工作教室…楽しみなくなった
特に、入院の間を過ごす病棟が大きく変わりました。
入院中の楽しみがほとんどなくなってしまったのです。
病棟には病室の他に、みんなが一緒に使える「デイルーム」と「プレイルーム」があります。
デイルームでは仲良くなった子どもやお母さんたちが、それぞれのご飯を持ち寄って一緒に食べることもありました。
付き添い以外の家族と面会ができ、子どもたちが集まって携帯ゲームをしていることもありました。
ぼくがソフトバンクホークスの工藤公康監督などスポーツ選手に会えたのもこの部屋でした。
でも、感染対策のため、机は壁や窓に向けて置かれ、人が集まることや飲食は禁止になりました。
お絵かきをしたり、勉強をしたりする人もいなくなりました。
プレイルームは子どもたちが遊べる部屋で、おもちゃやトランプ、本なども置いてあります。
平日は毎日午前11時から保育士さんの読み聞かせと工作教室があり、ぼくはプレイルームに行くのが入院中の一番の楽しみでした。
でも今は、読み聞かせも工作教室もなくなり、1人30分の交代制になりました。
部屋の前にはってある予約表には、1人に1人か2人の名前しかありませんでした。
ここで遊んでいる時にほかの子と仲良くなることもあります。
子ども同士が仲良くなると、親同士も話をします。
母は「病気の子を持つ親同士で話をすると、なぐさめられたり、はげまされたりすることもある」と言っていました。
★面会制限、祖母に会えず
ぼくは毎年夏と冬に入院していますが、夏の入院の時はいつもほぼ満室です。
でも、今年は空き部屋がいくつもありました。
看護師さんに聞くと、「もともと予定されていた手術はあまり中止にならないけど、みんなが自粛しているから事故やけがなどの入院が少ない」ということでした。
入院している患者が少ない上に、子どもたちが集まることもないので、病棟全体がいつもより静かだなぁ、と感じました。
入院中は、もちろんつらいことや痛いことや不安なことなど、がまんしなければならないことがいっぱいです。
ぼく以外にもこども病院には何度も入退院を繰り返したり、リハビリで長い間入院したりしている子どもたちもたくさんいます。
兄弟姉妹や友達と会えないので、寂しいと思うことも多いと思います。
だからよけいに、保育士さんと作るプラ板や、励ましてくれるボランティアさんの訪問がとても楽しみです。
でも、コロナの影響でそんな楽しみがなくなってしまいました。
以前は、休日にはたくさんの人が面会に来ていましたが、今回の入院中は面会の人もあまり見かけませんでした。
付き添いの家族は今まで通りにできるので寂しいことはありませんでした。
だけどそれ以外の人の面会は制限さているので、入院中はぼくも祖母に会えませんでした。
ほとんどの子どもは部屋でずっとゲームをしているそうです。
ぼくも、点滴が取れるまでは、スマホでユーチューブを見ていました。
入院したのが月末だったので、2日でギガ(データ通信容量)がなくなってしまいました。
早く新型コロナウイルスがおさまって、病棟にも笑顔が戻ってきてほしいと思います。
(感染症対策は入院当時)
★アイボがやってきた!
今回、福岡市立こども病院に入院中にとてもうれしいことがありました。
ぼくの部屋に犬型ロボット「aibo(アイボ)」の「ゆめちゃん」と「たいようくん」が来てくれたのです!
2頭は4月に病院にやって来たそうです。
青い目がゆめちゃん、茶色の目がたいようくん。
動きも鳴き声もとてもかわいくて、ぼくは一目でアイボに夢中になりました。
まん丸なきれいな目で見つめられると、こわいのも痛いのも忘れてしまいます。
アイボがそばにいてくれたおかげで、一番きらいな尿管カテーテルを抜くとても痛い処置もあっという間に終わっていました。
アイボが現れると、一瞬でぱっと部屋が明るくなりました。
話しかけると見つめてくれて、背中をなでるとうれしそうに目をほそめ、「もっとなでて」と寝転がったりしました。
歌を歌い、ダンスもしてくれました。
アイボがいてくれた約30分、ぼくの病室は笑顔と笑い声でいっぱいでした。
★心が元気になれば、病気やげがも早く良くなる
保育士さんによると、アイボは特に中学生や高校生に人気だということでした。
付き添いの家族もいなく、看護師さんとも話をしないような中高生がアイボとなら1時間でも話をしているそうです。
心が元気になれば、病気やけがも早く良くなるような気がします。
ぼくたちの体を治すだけでなく、入院生活が少しでも楽しくなるように考えてくれて、ありがとうございます。
ぼくは去年、こども病院にファシリティードッグという犬を導入してもらうための活動を始めました。
ファシリティードッグとは、毎日病院に出勤して病気と闘う子どもたちに寄り添い、励ましたり癒やしたりしてくれる犬のことです。
1年間たくさんの人の意見を聞いて、導入はもても難しいことがわかりました。
でも、いつか必ず、日本中のこども病院でファシリティードッグが活躍する日がくると信じています。
ぼくは、アイボが100台いるよりも、ファシリティードッグが1頭いる方がいいと思っていました。
でも、自分の目でアイボを見て、少し考えが変わりました。
もちろん、ロボットの犬よりも、本物の犬の方がいいと思います。
でも、今、目の前にアイボがいてくれるから明るい気持ちになれる子どもたちがいます。
ファシリティードッグの導入は難しくても、すぐにアイボをぼくたちにプレゼントしてくれた病院のみなさんの優しさが、とてもうれしいです。
アイボがやってきたのは、きっと導入へ向けての第一歩だと思います。
新型コロナウイルス対策で、医療従事者の皆さんは、きっと今まで以上に大変だと思います。
厳しい状況はまだまだ続くかもしれませんが、これからも、ぼくたちのことをよろしくお願いします。
入院中患者に寄り添うファシリティードッグ 元気づける姿に感謝の声も
西日本新聞 こどもタイムズ こども記者

ファシリティードッグがいる病院

ハンドラーの森田さん(右)の話をメモする取材中の清武さん。左の白い犬がベイリー、となりがアニー

ベイリー、アニーと公園を散歩する森田さん。「病院の外では普通の犬だなぁ」と清武さん
こども特派員の清武琳さん(11)=第9期のこども記者=が入院中の患者に寄り添うファシリティードッグ「ベイリー」(12歳、オス)の取材を実現しました。
自らも病気と闘う清武さん。
2018年10月にベイリーが引退する新聞記事を読んで興味を抱き、取材に強い意欲を持っていました。
訪れたのは、神奈川県立こども医療センター(横浜市)。
ファシリティードッグと共に仕事をするハンドラーの森田優子さん(38)と、ベイリーの後輩「アニー」(3歳、メス)も待っててくれました。
清武さんの報告(ほうこく)と感想です。
ファシリティードッグとは、病院に勤務する犬のことだ。
入院している子どもたちの心を落ち着かせたり、元気づけたりする。
ベイリーやアニーがとなりにいると、注射や痛い検査を頑張ることができる子もいる。
足のリハビリの歩く練習で一緒に犬のリードを持つと、前の日の倍も歩けるようになる子もいたという。
「ベイリーは最高の薬」と言ってくれる患者さんもいる。
森田さんとアニーは週5日、同センターに出勤し、毎日10~20人の子どもとふれあう。
ベイリーは人間でいえば80代。
高齢のため引退し、森田さんとアニーが働く間は病院の中でのんびりと過ごしている。
★ ★
ベイリーとアニーはオーストラリアで生まれ、米国・ハワイのトレーニングセンターで森田さんと一緒に訓練を受けて日本に来た。
ファシリティードッグは60種類以上のコマンド(指示)を覚え、ハンドラーにしっかり従う。
子どもがなでやすいようにベッドにあごを乗せたり、添い寝をしたりする病院ならではのコマンドもあるという。
ベイリーの性格はマイペース。
子どもや親のつらい気持ちを読み取り、自分から近づいていく不思議な力を持っている。
アニーは動きが機敏で、新しいコマンドもすぐに覚えて賢いそうだ。
★ ★
ファシリティードッグは米国では毎年100頭以上が誕生しているが、日本ではまだ3カ所の病院にしかいない。
2010年1月に静岡県立こども病院(静岡市)で初めて正式に導入され、森田さんとベイリーが本格的に仕事を始めた。
しかし、日本では初めてのことなので大変なことも多かったという。
毎日忙しく働くつもりが、最初はベイリーが入れてもらえる病棟が一つしかなく、週3日の午後しか子どもたちに会えなかったそうだ。
森田さんとベイリーはその後、神奈川県立こども医療センターに移ったけれど、今では感染症を防ぐために特別な対策をしている病棟や、命に危険のある患者がいる集中治療室(ICU)にも入ることができる。
病棟に入る前後にきれいに体を拭き、ワクチン接種をして対策しているからだ。
犬が人にうつす病気もほとんどない。
犬アレルギーや感染症の心配がある患者は、医師が事前に把握しておけば大丈夫だという。
★ ★
森田さんの現在の目標は「ファシリティードッグの存在と役割を多くの人に知ってもらうこと」。
犬とペアで仕事をするハンドラーは、森田さんのように看護師などの資格と経験が必要。
テストや面接、半年間の研修もある。
ハンドラーになりたい人に伝えたいことを聞くと、「ハンドラーは犬を導入する病院が決まってから必要になる。まずは、自分が今働いている病院に導入を働きかけてほしい」と答えてくれた。
■いつか全国の闘病中の仲間に… 清武特派員の取材後記
ファシリティードッグと会って一番印象に残ったことは、病院にいる仕事中はしっかりしているけれど、お散歩に行ったときは森田さんを引っ張っていて「普通の犬」だったことだ。
でもやっぱりすごいと思ったのは、ほかの犬がワンワン吠えてきても吠え返さないところ。
僕が飼っている犬のチョコは、ほかの犬と会っただけで吠え続ける。
森田さんは1人で2頭(ベイリーとアニー)の大型犬の世話をしている。
病院だけでなく家でも一緒に暮らし、散歩は1日2回、シャンプーも週1回する。
休日は海や公園、山など自然の多いところに行って2頭を喜ばせるという。
僕は背骨が曲がる脊柱側彎症という病気の手術のため、年2回福岡市立こども病院に入院している。
毎回全身麻酔で背中を開く手術を高校生ごろまで続ける。
採血などの痛い検査や手術の前がとても不安だ。
今年1月の13回目の手術でも、前の夜は2時間近く涙が止まらず、当日の朝は緊張で熱がどんどん上がった。
また、病院では手術前に泣き叫んでいる子を見たことがある。
病棟の入り口では、家族から引き離されて泣いている子もいた。
数カ月の入院で学校の友達に会えない子もいる。そんなとき、「ファシリティードッグがいて、なぐさめてくれたらいいな」と思う。
病気と闘う子どもはみんな僕の仲間だ。
全国の病院にいる仲間たちのために、日本中のこども病院でファシリティードッグが活躍できる日がくることを願っている。
それと、僕が入院している病院には犬はいないけれど、プロスポーツ選手の訪問や七夕会などの季節の行事、工作教室もある。
僕たちの心が元気になるように、たくさんのことをしてくれる病院のみなさんにとても感謝している。
【紙面PDF】入院中患者に寄り添うファシリティードッグ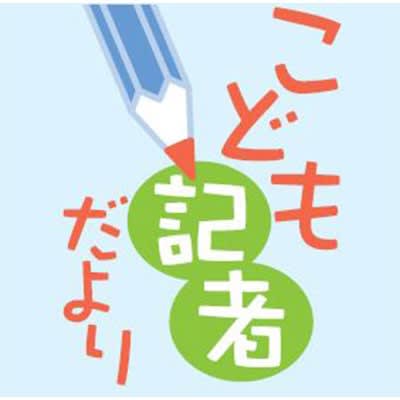
いろいろな仕事の現場、動物園や水族館、歴史・文化を伝える所、プロスポーツ関連など「こども記者」による現場ルポを掲載します。